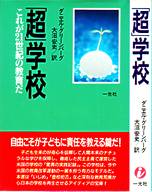1965年、グリーンバーグ夫妻は4歳(注:USAの就学年齢)の我が子をどの学校に入学させようかと考えるが、なかなか良い学校がみつからない。良い学校とは、子どもと社会が出会う場所、子どもと社会双方が必要とする場所。そう考える夫妻は当時の学校に不満を持っていた。科学者のダニエルは子どものころから勉強に明け暮れ、我が子にはそんな子ども時代を送って欲しくなかったし、ハンナはダニエルと正反対の自由な子ども時代を過したので、子どもを自由の空気のなかで育てたかった。それでお互いの考えが一致、SVS誕生へと向かった。
学校は産業化社会のなかで生まれ、今また情報化へ向かう社会のなかにある。大きく社会が変化するとき、次世代を担う子どもに社会は何を求め、また子どもはその社会にどうコミットしていくのか。そう考えると、教育や学校のあり方を情報化社会のなかでどうとらえればいいのだろう。
SVSを創り運営していくなかで、独自の学習感や社会感、教育感をダニエル夫妻も学んでいったように思う。実践の中から生まれた思想は多くの示唆に富んでいる。この講演では大きく3つの視点からのお話と質疑応答が聞けた。(1999.4.29
上智大学にて)
■ 目 次 ■
1.子どもについて
2.社会について
3.双方の出会う場としてのSVSについて
4.質疑応答
(1)SVSの入学条件について
(2)卒業、中退、退学、不適応について
(3)苦労、内部批判はないか
(4)授業料や運営資金について
(5)チャータースクールについて
(6)スタッフとティーチャー
※付記(1999.05.29 巻頭コラムより)
この電子書簡集は、1997年2月〜10月にかけて私(田尻=ポップンポール)と教科書編集者・堀畑仁宏氏との間で交わされた教育談義に若干手を加えて収録したものです。
そもそもはサドベリーバレー校(SVS)がおそらく日本にはじめて紹介された『「超」学校』(一光社)を、私が某出版社の社内掲示板で礼賛したところから始まりました。本来はクローズドな掲示板ですが、堀畑氏の了解を得て公開するものです。
お互いにシンパシーを感じながらも、教育に対する考え方やスタンスが異なり、なかなか充実した内容になっていると思います。教育にあらかじめ用意された正解はありません。それぞれが個々に考え、実践し、ときには失敗しながら格闘していく、その過程こそが大切なのだと思います。
この電子書簡集は未完です。きっと終わりはないでしょう。しかし一つ一つの文章を書く上で考えたことは大変貴重な経験です。それをこうして公開してゆくことも、また大切なことだと思っています。公開を快諾していただいた堀畑氏に感謝するとともに、もっと多くの方の意見も聞いてみたいと思っています(掲示板やメール等で感想をいただけるとうれしいです)。
日本にもサドベリーバレー校のような学び舎が一日も早く誕生することを願ってやみません。
□ 目 次 □
私の教育論をほぼ100%実践している学校紹介(田尻)
共感するけど、抵抗感もある。(堀畑)
究極の理想と現実の狭間で出来ることはなにか考えたい(田尻)
なんで学校が必要なの? それが大事(堀畑)
違いのありかをみつけていきたい。(田尻)
教育とは学習へのはたらきかけ(堀畑)
教える側の動機のありか〜未完によせて〜(田尻)
付記:SVSのなかの特殊なひとりの子(田尻)
画像をクリックしますとオンライン書店amazonから購入できます。
日本ではサドベリーバレー校を紹介した書籍は大変少ないです。日本の教育制度の枠内では実現不可能、夢物語じゃないかという諦めや、学習に対する個人の自由と教育の民主化が根付いていないことにその原因があるのかもしれません。しかし学習を個人の手に取り戻し、民主的な学校が現実に存在することを知ることから始めませんか。